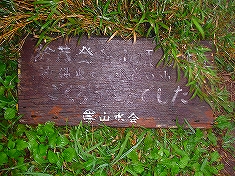87号線の於茂登地区から道標に従い林道を入る。ここには大きな公式な道標があり見落とすことはない。ここから舗装路を1.4キロ進むと、右側に林道が分岐しており、ここに右折する。曲がり角には私的な道標が付いている。舗装路はすぐに途切れ、石の露出したダート林道となる。分岐から350m程のところで行き止まりとなり、ここが登山口となる。駐車スペースは、回転を考えると6台~7台くらいだろうか。
前夜に到着したのだが、雨が強く降り、時折雷鳴も聞こえている。まったくもってひどい天気となった。350のビールを2本空け、横になるが、ボンネットや屋根を叩く雨粒の音で寝られたもんではなかった。結局、一度も降り止むことなく朝を迎えたようであった。
雨具を着込み、いざ出発。コンクリートの敷かれた道をヘッドライトで歩いてゆく。いきなり丸太橋の通過箇所があるのだが、濡れていてよく滑った。登山口にもあったのだが、「山水会」が道を管理しているのか、適時に道標が付けられている。不思議な文字使いの、「大御岳ぬ清水」と書かれた石碑があり、しばらく沢に沿うように登山道は進んでいった。数度沢を跨ぐところがあり、その最後の場所には「最後の水場」と書かれている。水を飲んでみたが、八重島諸島での水は、ほとんど生温い感じがする。何も無い場所では、水があることだけでもありがたいのだが、本土での冷たい水に慣れてしまっていると、この温度はやや違和感を抱く。相変わらずコンクリートは敷かれており、このまま山頂までこの調子なのかと思ってしまう。
今日も完全にサウナ状態であった。しかし雨も降りやまず、脱ぐことはできない。途中で傘に切り替えたのだが、ふと雨具のズボンをみると黒い細長い生き物がくっついていた。蛭である。ここも蛭が多いようで、前日にひどい目に遭っているので、再び雨具を着込んだ。山頂が近くなると急登の場所になるが、しっかりロープが流してあり、安心して通過はできる。このロープ、ザイルと言うより
は海用のもののようであり、島国らしいと思えてしまった。
ここでも山頂が近くなるとチシマザサが出てくる。途中左に広い切り開きがあり、そこを上がって行くとフェンスに囲まれた気象用のアンテナ施設があった。ここがよくラジオで気象情報を流しているところの「石垣島、風力・・・・」の場所であろう。登山道に戻り、先に進むと手前にテレビアンテナ施設があり。そこから左に巻き込むように進むと山頂があった。この山頂にある三角点は、新しいのか左から右へ文字が書かれていた。
帰りに無線のレピーター施設を見るが、アンテナが上がっていないようであった。そして途中のダム湖展望台にも寄ってみる。こちらには古いアンテナ施設があり、現山頂にある以前に使われていたもののようであった。周囲にはフェンスがあるのだが、門扉は開け放たれた状態であった。ガスに覆われ、残念ながら展望がなかった。
往路を戻って行くと、ここでも登山道上にセマルハコガメが居た。この亀は陸上に特化しており、その脚力の速いこと。こちらの姿を見るや、すぐに藪の中に消えていった。登山口まで戻っても相変わらず雨が降りやまず。すでに全身ずぶ濡れであった。
ここは上部の方で、地形図の破線とは違う所を歩く事になる。新しい道に対して地形図の改訂がされていないのであろう。