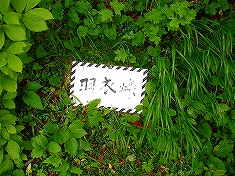「蝦夷」が「北海道」と名前を変えて今年で140年目となる。そんな節目でもあり、久しぶりに出向いてみることにした。北海道に行くには飛行機か船になるのだが、我が家からだと羽田に行くのも新潟に出るのもさほど変わらない。船の場合は時間的な部分で飛行機には劣るが、そののんびりさ故に旅心をくすぐる。はっきり言うとフェリー好きでもあった。各社ある中で断然の安さから「新日本海フェリー」の選択となるが、大型連休時は利用者が集中し、一昔前は電話に齧り付きで予約を入れたものであった。しかし昨今はインターネットでの予約が出来るようになり、以前に比べると格段に楽になった。ただ、それにしたところでハイシーズンであり、利用率は高い。何とか滑り込みで予約が出来、旅の準備が整った。
今回の行き先は知床とした。世界遺産で騒がれている場所であり、一度その岬を見てみたいと思っていた。となると登る山は羅臼岳から硫黄山までの山が適当である。しかし現在は硫黄山への登路が封鎖されているので周回計画は無理であり、縦走は後日として今回は羅臼岳のみを目指すこととした。北アルプスで治癒した肺の状態も良く、快調にて旅の出立を迎えることが出来た。
家を18:10出発。関越道に乗り3枚のETCカードを繋いで通勤割引を使いながら新潟港へ。ターミナルへの到着は21:10であったが、既に北の大地に向かう車列は幾重にも出来ていて、先頭から数えて5列目の後方に並ぶ。そして案内所で往復の手続きをする。この時、予約の方の場合はクレジットカード払いとなる。クレジットカードの番号が利用者登録時に登録され、本人照合と支払いの省力化となっているのであろう。
乗船し出航は23:30。寝台が取れなかったので、2等和室の入り口付近に陣取る。往復で判ったのだが、昨今はコンセントの有無が重要になる。船のコンセントはその殆どが携帯電話に占領させる。2等船室の場合、そのコンセントは海側と更衣室に2箇所あり、更衣室の広いスペースが誰の割りあてにならず空間として開いている。その横に陣取るのが広く使え便利であった。当然コンセントもいの一番に使え、空き状況もつぶさに把握できパソコン用電源としても使いやすかった。風呂に入りビールをあおる。波静かで船は18ノットほどで北上してゆく。翌朝は天候も良く、後部デッキのジャグジーの所でぼんやり。そして波静かで30分早く到着(17:00)。
苫小牧東港から知床に向けて快調に走るが、足寄地内でトルコンが異常動作をしだし、自動ではシフトアップをしなくなり、さらには4速に入らなくなった。トルコンが滑っていふうでもなく、異常原因が判らずJAFを初めて呼ぶことになった。これは上陸1日目から大ブレーキとなった。頭の中が真っ白になり、予定表に書かれた7日間の観光地が消しゴムで消されてゆくような心境であった。結局現地では処置できず、このまま騙し騙し乗ることになった。いやはや前途多難とはこの事であろう。おかげでだいぶ時間のロスをして00:50、羅臼岳のウトロ側の登山口となる岩尾別温泉に到着する(苫小牧から450Km)。
翌朝は4:00起床、周辺に停めていた数名が既に出発して行っていた。こちらも急いで朝食を取り、4:35スタートとなる。温泉の駐車場前の余地に停めたのだが、ホテルの右脇をさらに行くと、登山者用の駐車場があり、その先に登山口となる木下小屋があった。トイレの臭いが強烈に漂う前を通過し、山道に入る。注連縄をくぐり、よく踏まれた道を行く。緩やかに切られた道は非常に歩きやすく100名山を感じる。
歩き出しから30分ほどすると「熊出没事例」の案内看板がある。登り出し初期の段階から登山者に注意を促す目的もあるのであろう。少し周囲を気にしながら歩いてゆく。そしてこの先で、ルート途中で唯一海側の展望の開ける「オホーツク展望台」がある。西側が樹木に遮られてはいるが、ウトロ側の展望はいい場所であった。斜里岳も遠くに望め、自然と足を止めたくなる場所であった。この先も歩き易いなだらかな道が続く。
随時に標柱があり、残り距離や地形名が書かれていた。弥三吉水では冷たい水が流れているのだが、どうしても北海道の場合エキノコックスが気になる。ただしここの水は流水であり、この辺の問題には引っかからないであろう。飲まないことに越したことはないが、せっかくの水場、コップも用意されており喉を潤す。地形図を見るとイワウベツ川の源頭にも当る場所であり、こんなに海と近い場所が源頭となるのは知床ならではなのかと思った。
次に極楽平の平坦地を通過、ここからは山頂側の高みを望むことが出来る。砂地には無数の鹿の足跡が残り、それにより自然と一体感が増す。仙人坂を経て次の水場の銀冷水の場所になるが、沢には流れがなく、少々奥の方に詰めてみたが水気は全くなかった。夏の一番欲しい時期に涸れてしまっていた。この辺りからだんだんと登山道上に岩がごろごろとしだし、やや足場が悪くなる。大沢に入るとその度合いが増すのだが、ここはお花畑でもあり、それらを愛でながらゆっくりと足を上げてゆく。白いガイドロープが登山道の両側に張られ、沢が踏み跡で荒れるのを防いでいるようであった。
大沢を登りきり羅臼平に到着する。ハイマツの平原であるが、南北にある羅臼岳と三ッ峰があることにより、その展望から居心地の良さが増す。テントが3張りあり、前日登り上げここで幕営したようであった。話を聞くと前日ここでヘリが飛ぶような事故が起きたらしい。テントを周辺に居る人の顔が浮かない顔をしていたのはその為か。熊から食料を守るためのフードロッカーも置かれ、この金属の箱により、熊の存在を身近に感じたりした。しばしの休憩で山頂へ向け足を進める。
ハイマツの回廊に足を進めると、登路脇の岩場に小動物が動いた。鳥かと思ったら3匹のシマリスであった。こちらの存在を判っているのであろうが、全く気にしていないように岩場を遊び場にしていた。羅臼側への2度目の分岐を過ぎるとそこに岩清水があり、冷たい水が岩から流れ落ちていた。この水は幾分硫黄の風味がするような・・・。力水とばかりに喉を潤し、この先の岩場に入る。大きなゴーロ帯と言うのが正しいのか、わりと角の立った岩があるので、手を置く場合は注意したい。皮膚の薄い同行者はここで手を流血をしていた。岩には赤ペンキでルートが示されているが、かすれている場所も多く、それを探すように上を目指す。
7:53羅臼岳山頂に立つ。もう少し時間がかかるのかと思っていたが、休憩を入れながらゆっくり歩いても3.5時間ほどで到達したことになる。羅臼側は真っ白、見たかった国後島はそのガスの中。他の方角は舫っているものの何とか見渡すことが出来た。山頂は当然岩峰なのだが、そこから20mほど下がった岩場(東側)には、白ペンキでの落書きが目立った。某大学などと書かれたものもあり、これも世界遺産になってしまったということか。確かこんな場合消せなかったはず。山頂には私を含め5名が登頂しており、その中の一人は百名山信者であり、しきりに各百名山の情報を話していた。信者には有益な話なのであろうが、どうでもよい私には右から左に・・・。展望を一通り楽しみ、山頂部の岩場に目を向けると真鍮製の二等三角点があった。傷が入れられ「二」が「三」になっているが、全体的な文字配列から察すると二である。よくよく真鍮製の四等点は見るのだが、この形状での二等点は初めてであった。しばし羅臼側のガスが晴れるのを待ったが、様子は変わらず下山となる。
下り始めは慎重に行かないと、ちょっとしたスリップが大怪我になる。カメラを抱えたハイカーが多く、やはりこの展望は誰しもカメラを離せないのかもしれない。大沢辺りからすれ違う人も多くなり、外国人の方も多い。中には100リッターほどの大荷物の方も居たが、硫黄岳側への縦走か。さらにはバイカーがライダーシューズのまま上がってきていたり千差万別、いろんな姿の方がすれ違って行った。いつもの通り同行者は膝痛となり、ゆっくりと様子をみながら下ってゆく。
総勢50名ほどとすれ違い、登山口の岩尾別温泉に降り立ち羅臼岳の登山を終える。予想以上に歩きやすい登路であった。もう少し勾配の厳しい場所であると思ったが、よく踏まれていることもあり、足を運ぶのが楽なルートであった。車に戻りザックを放り込み、すぐさま地の涯の露天風呂に沈没。大自然のいで湯に浸かりながら目を閉じる。先ほどまでの壮大な景色を思い出しながら極楽極楽・・・。