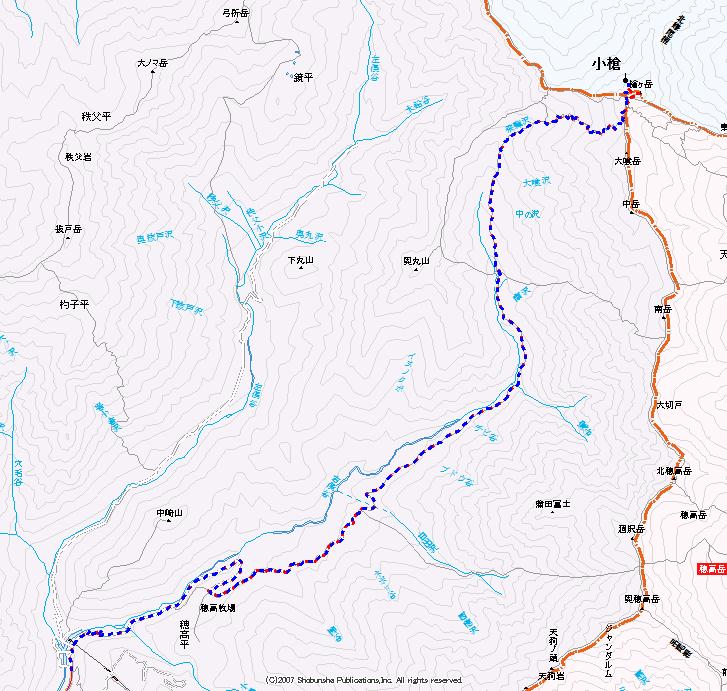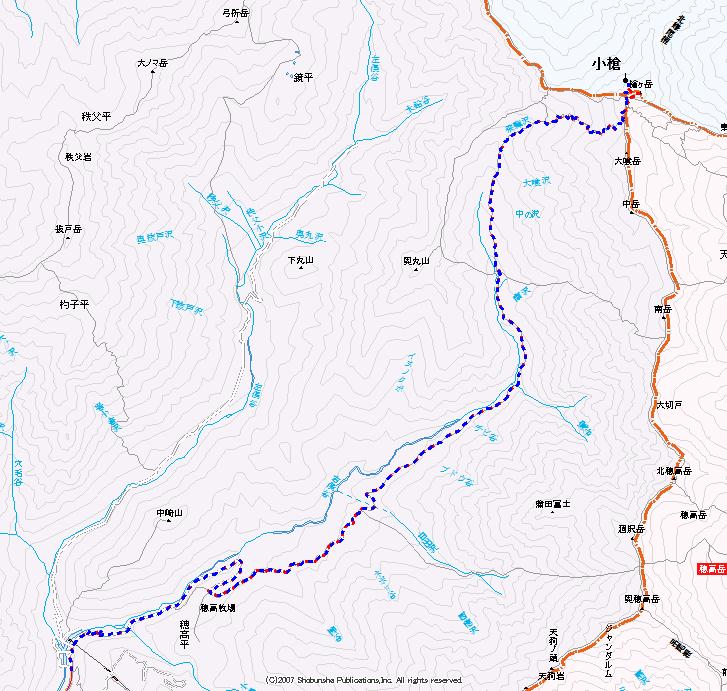「♪ アルプス一万尺 小槍の上で・・・」、この歌は老若男女のどなたでも歌える歌であろうが、そこに出てくる小槍の上で実際にアルペン踊りをした方は、本当に数えるほどであろう。そこには、登頂しても大槍から見られているので恥ずかしくてアルペン踊りなど出来ないと言う部分もあるのだが、踊りはどうでも良いとして、登頂するには高度感のある4級の岩場が待っている。そして登ったら、下るには50mの懸垂下降をせねばならない。したがい、大槍と違い誰しもが近付ける場所とは違う。
私の未踏のジャイアンツ(3000m峰)も、残るはロバの耳とこの小槍だけとなった。ロバの耳もちょっと岩の上を伝う形になるが、この小槍は、岩は岩なれどクライミングの世界となる。その為、どうにも独りでは手も足も出せない場所となっていた。気になりつつも行けない場所、そこが小槍であった。当然のように岩屋さんが沢山登っているが、私は岩屋であらず世界が違う。やはり高いハードルの先に小槍はあった。そこにひょんなタイミングで、甲州のオールラウンダー薮山愛子さんから連絡が入った。薮山さんは幾多の岩壁の経験を持ち、アイスクライムまでやる実力のある大先輩であった。考える事無く「小槍に行きたいのですが・・・」と持ちかけてしまった。すると二つ返事で「OK」の回答が届いた。さらには力強い事に、滋賀の雄であるI氏も合流してくださる事となった。さらにさらに愛知の女傑Kさんの合流が決まり、私以外は玄人岩屋のパーティーとなった。いやはや凄いメンバーが集結する事となった。持つべきものは友と強く思う半面、「邪魔をしないか」「足手纏いではないか」、そんな事ばかりが頭を過ぎる。何せザイルを使うにしても、殆ど肩がらみで使うことが多いのであるから、基本的な部分がなっていないのが私である。予習をしようと、色々と本を読むが、やはり体に教え込まないといくら本を読んでも現実感が無い。あるところから先は、当たって砕けろであった。砕けてしまっては困るが・・・。
1:20家を出る。出掛けに各天気予報サイトを確認すると、土曜日は良さそうで、日曜日が不安定となっていた。さあどう転ぶか・・・。三才山トンネルを越えて松本に下り、158号で安房トンネルに潜り込む。トンネルを抜けるとゲートなのだが、今日もつり銭が機械から落ちた。「落ちる」とは不穏な事なのだが、落ちたのはこれで3回目。管理の方、何とかしてください。受け皿が懐の薄いアルミ製。そこに勢いよくお金が落ちてくるので、当たり所で跳ねてしまうのであった。冬場の1回は、拾うのを諦めた事もあった。硫黄の香りを嗅ぎながら新平湯の温泉街を下り、栃尾で右折して新穂高に向かう。さて夏山開きが終えた後、駐車場の状況はどうだろうと、恐る恐る近づいて行く。そして深山荘の入口を下って行くと、先の方で車がごちゃごちゃと動いている。もしや駐車場がオーバーフローに・・・と思ったが、近づくと、駐車場への進路を間違え常陸ナンバーの2台がユーターンしていただけであった。駐車場は意外やスキスキで、一番上層の駐車場には15台ほどが停まっているくらいであった。そこに近江ナンバーの車を見つける。今日のリーダーのI氏は既に到着しているようであった。そそくさと車を白線内に納め、仮眠となる(4:35)。ただ既に夜が開け、スタートする方々もある。先ほどの常陸ナンバーのパーティーは10名ほどのパーティーで、到着後すぐにぞろぞろとスタートして行った。こちらはしばし夢見心地に・・・。
集合時間の6時が近くなり準備をしだすと、そこにすらりとした紳士が現れた。I氏であった。噂は予てから聞いていたが、逢うのは初めて。挨拶を交わし、今回の岩場での牽引役をお願いする。そうこうしていると、甲州から薮山さんと尾張からKさんが到着した。揃うと皆、贅肉の無い岩屋らしい体躯をしている。危険度の高い場所に挑むために鍛錬し、体全体が岩を登るが為の道具に成り得ているのであった。Kさんとも今回逢うのが初めて、丁重に挨拶をする。このKさんは、3000座登頂者を輩出した某無線登山家集団において、女性ではトップのクライマーである。各人の準備を待つ間に、蒲田川を見下ろすと、轟音と共に白い激流となった流れがあった。すぐに白出沢と滝谷の現地が気になった。以前、現在のような水量の時、白出沢が渡れない時があったからだった。今回の言いだしっぺは私であり、白出沢までで引き返す事になっては、遠方から来ていただいた方に申し訳なく、それが強く気になった。目指す高みを見上げると、完全にガスの中。不安を抱きつつ「よろしくお願いします」と発し、スタートを切る(6:00)。
ターミナル前は閑散としていた。右岸側の工事が進み、左岸側にもその影響が出ていた。ロープウェーの先の駐車場には3台のみ。時間的に少し早いが、これが梅雨時期の現実なのかとも思えた。右俣林道沿いには、美味しそうなミズが生え、何本か摘んでボリボリと貪る。水分量が多く、クセが無いので歩きながら食べるにはちょうど良い。中部山岳国立公園としてみてしまうと、採る事は怒られそうだが、林道の左右は草刈がされており、私の行為もある意味草刈と同じと解釈されたし。久しぶりのパーティー行動。賑やかに歓談しながら足を出してゆく。
小鍋谷のゲートに来ると、必ずと言っていいほどに東の薮の中に目が行く。車を入れられた当時を懐かしんで、その駐車場の場所を見てしまうのであった。穂高平まで4人で足を揃えて来たが、ここから一人抜け出て先を急ぐ。パーティー行動にあるまじきはみ出し行為だが、最初から槍ヶ岳山荘に夕刻集合と言う計画であり、道中の行動は自由となっていた。白出沢が近くなると、銀色のワンボックスの軽四が2名を乗せて追い越して行った。奥穂側の関係者か、はたまた槍側の関係者か、恨めしく見ながら土埃の後を追う。そして目の前の緑が白く明るい場所に変わる。白出沢に到着した。懸案の流れは、全く問題ないほどのチョロチョロとしたものだけであった。この分だとチビ谷は大丈夫だろうから、残すは滝谷か。石の上をピョンピョンと伝いながら、そんな事を考えていた。
林道歩きが終わりやっと山道に入る。同じ歩くにしても林道歩きより山道の方が楽で、少しスピードアップとなる。するとチビ谷を手前にして常陸からのパーティーが休んでいた。メンバー内にはザイルを背負っている方も居る。しかしどう見ても岩をやるように見えない方も中に居り、行き先が頭の中で絞れなかった。最終的には大槍へのサポート用のザイルかと思えたのだが、この思いの色々はこの先に続く。相変わらず右俣谷の流れは轟音で、重く強い流れが白くそこにあった。次の滝谷を越してしまえば水に対して不安箇所は無いが、なにせまだそこまで到達しておらず、右俣谷の流れにこの先の不安が増す。天気は回復傾向にあり、時折強い日差しを浴びられるほどになった。それでも外気温は12度。とても涼しく快適な山歩きとなっていた。
ブロック積みの滝谷避難小屋が見え、その先に広い滝谷が広がる。しかし予期していた通りに、大きな流れがそこにあった。左岸側から右岸に移れず、右往左往している先行ハイカーの姿もあった。上流下流とずれても、簡単に渡れる場所が見出せず、大岩の場所のワンポイントが、辛うじて濡れずに渡れる場所であった。渡ったからとて安心できず、まだ先にもう一本流れがあり、ここも厳しい場所となっていた。ただ、見ていると右岸側にいる菅笠を被った方の体躯がかなり山慣れして、長靴を履きピョンピョンと岩の上を移動している。どうやら槍平小屋の小屋番のようであった。軽く会釈をすると、無言で返してくれた。そうこうしていると、先ほどの常陸からのパーティーが到着した。すると迷う事無く滝谷を上流に詰め始めた。“滝谷をやるのか”と思ったが、見えているパーティー内の女性は、どうにも岩屋には見えない。先頭のリーダーはかなりの精鋭のようだが、向かう方向に対してちぐはぐで、理解に苦しんでいた。避難小屋の場所から70mほど遡上していたが、流れが強く進めずに下ってきた。そしてそれを見ていた小屋番(たぶん)が近くに縛ってデポしてあった角材で橋を造ってくれ、最初の流れ、次の流れと順番にずらして彼(彼女)らを渡してやっていた。彼らが右岸に移ると、当然上流に向かうのかと思ったが、そのまま槍平側に足を向けて登山道付近で休憩となった。結局普通に槍を目指すパーティーだったのだ。さて他人の動作を暫く楽しんでいたのだが、ここはピンポイントで渡らねばならず、後からやってくる3名を待つ事にした。川の中州に陣取り、上流を見上げながら涼む。雪解けの冷たい流れが周囲温度を下げ、ここではとても涼しく快適に居る事が出来た。ちらほらとやってくるハイカーを、小屋番は丁寧に渡渉の導きをしていた。優しい方である。
滝谷到着後、45分ほどしてKさんを先頭に順番に滝谷に入ってきた。やはり渡渉場所が見出せないようで、その場所を導き、短時間で右岸に移ることが出来た。少しは斥候役として力になれたか・・・。上の岩場では助けてもらわねばならないので、このくらいはしておかないと・・・。そしてまた先行する。するとその先に居た常陸のパーティーをすぐに捕まえた。風貌から、「学生ですか」と聞いたら、「社会人で、会社の仲間です」と返って来た。見る目がないと反省し「失礼しました」とすぐに謝る。さらに装備から「槍で幕営ですか」と聞くと、男性は幕営、女性は小屋泊まりなのだそうだ。女性に優しい山岳クラブなのであった。この辺りの登山道の両側は、草刈がされ、綺麗に管理されていた。先ほどの小屋番の顔が浮かぶ。
槍平小屋到着。なぜかいつものようにクンクンと鼻を動かす。しかしいつもの臭いがしない。槍平小屋の以前は南側にトイレがあったので、到着時にそこからの臭いがいつも強くしていた。しかし今回はそれが無い。トイレは小屋の北側に移したようで、快適に休憩できる場所に変わっていた。テント場には僅かに一張り。山開きはしたが、ここはまだ冬覚めやらぬ静かなままであった。水場で500mlのプラパティスを満たし、先を急ぐ。ここの取水は、シンクから後ろ(東)を振り向くと、標高差30mほどの場所に黄色いポリタンクが見える。その沢から取水しているようであった。
だんだんと足上げ量が増してゆく。時間の経過と共に辛くなってくる時間だが、かえってこの傾斜にアドレナリンが出でくるようで、快適に足が前に出て行った。それには飛騨沢の中に入ったこともあり、登山道脇のキヌガサソウやシナノキンバイなどの出迎えがあったからかもしれない。千丈沢乗越への分岐箇所には、救急箱が設置されていた。昨年訪れた時には無かったので夏以降に設置されたものらしい。優しい配慮である。でも靴が剥がれたら、登らず下ってくださいと書いてあった。ここまで来て帰るのは心中察するが、書いてある指摘に間違いはなし。飛騨沢にはまだまだ雪渓が残り、流れの出ている所が多い。夏道が雪に覆われ、マーカーのシノダケを拾いながら高度を上げてゆく。ただ、微妙に夏道に乗ったり離れたりで、ルートとして何処が正解なのかよく判らない状態であった。見上げると西鎌尾根へ続く岩峰がガスの中から姿を現す。どうやら上の方もだんだんと晴れてくるようである。なんとも嬉しい気分になり、少しばかりか足早になる。
飛騨沢を登りあげるのは9年ぶり、大喰岳の斜面が見えてくると、久しぶりにここに来た感慨が湧いてくる。そして飛騨乗越に到着する。眼下に雪を従えた殺生ヒュッテの赤い屋根が見え、その先にヒュッテ大槍が天空の城のように建っている。目を凝らすと槍沢の雪渓の上をポツポツと登りあげてきているハイカーの姿も見える。皆あの鋭利な穂先を目指して歩いているのである。3000mを越え、気温は9度となった。病弱な肺は、僅かな空気の薄さをはっきりと捉えており、肺の膨張収縮が非常に重くなる。でもそんな事を気にさせないような大展望であり、ことに表銀座の稜線は見事であった。九十九折をテント場を見ながら登りあげると、綺麗に建て変わった槍ヶ岳山荘の右側に、スクンとした大槍がこちらを見下ろしていた。
槍岳山荘に来たのは10年ぶり、飛騨乗越経由で大喰岳に行ったのも2000年だから、2002年10月に新築増設された山荘を、間近で見るのは初めてであった。小屋前から大槍を見上げると、岩壁にカラフルな雨具を着たハイカーが20人ほど取付いているのが見える。今回の目的地は大槍ではないのだが、ここまで来て登らずに帰るのは何か違う気がして、ザックをデポして大槍に向かう。適度な岩場を楽しみながら這い上がってゆく。梯子に手を掛けると、頂上からの歓声が聞こえてくる。なにかこの上がコンサートか、演舞の舞台になっているような、そんな歓声の大きさであった。
梯子を登り上げ、槍ヶ岳大槍登頂。周囲を見ると、確かに声を上げたくなるような展望がそこにあった。西側の展望はややガスの中だが、それ以外はくっきりすっきり見えている。久しぶりに大槍に登って、日頃の山座同定のブレを修正した感じとなった。既に踏破した山々、それと相対するこれから登らねばならない山々がしっかり見据える事ができた。日頃はこの大槍を見つけて周囲の山を把握していたのだが、ここを中心にすると、不思議と周囲の山々の名前がすらすらと出てくる。やはり槍は北アの中心的存在で間違いないのだろう。祠の北側に回りこみ、北鎌尾根を見下ろしながら風を受ける。後ろからは相変わらずの歓声が止む事がない。こちらも内心は歓声をあげたいところだが、グッと堪える。そして一番に目をやりたい場所、小槍を見下ろす。大槍から見ると、一見簡単そうにも見える。ただ、小屋側から見た場合は、ここから見るような柔和な顔はしていなかった。明日あそこに立てるのかと、岩肌のおおよその形状を目に焼き付ける。登頂者の殆どは、その景色に長居の方ばかりであった。ここでアルペン踊りの事前練習をと思ったが、恥ずかしがり屋の私にはそんな事ができるはずもない。鉄のはしごを下りだす。
下りながら、やはり小槍が気になり、直下まで今日のうちに行ってみる事とした。鉄梯子を二つ降り、ルートが登りと下りと分かれる場所がある。復路側からだと、ちょうどコルのようになっている場所を抜けると、往路側のルートに出る。そこから下を覗くと、ガレたルンゼが下に降りている。ここの石は殆ど動き、単独だからいいものの、複数人居たら危ない通過点である。実際に縦700mm、横500mmほどの岩を落としてしまった。下に人が居たら無事ではなかっただろう。それ以降かなり慎重になるが、重力には逆らえず、私の僅かな踏み出しに反応して、大量の石が落ちてゆく。20mほど下ったか、孫槍側の岩壁に一筋のバンド帯が見えた。そこに伝って西側に回りこんで行く。だんだんと目の前に小槍が迫り、その威圧感にどんどん気持ちが萎縮してゆく。内心、スキあらば登ってしまおうかと思っていたが、そんな思いは瞬時に消え去った。直下に到着。ここが山頂を踏んだ方のランディングポイントであった。コルへは6mほど北側に岩壁を登る。登りきると、そこにビレイ用のハーケンがかなり錆びた状態で2枚打たれていた。小槍を見ると、その岩壁にも要所要所にハーケンが打たれていた。正面のカンテ左側にはシュリンゲが下がり、ルート取りが何となく見えてくるようであった。今登る事は絶対に無理、明日に賭ける。戻りながら小屋側の岩尾根を見ると、そこに右上から左下に流れるようなきれいなバンドが見える。そこを狙うように進むと、ガレルンゼ内は3mほど上に伝うくらいで危険回避されバンドに乗る事が出来る。そして尾根を乗越す感じとなり、その先の岩場には橙色の細引きが付いたハーケンが打たれていた。ルートとしてはやや不明瞭だが、何となく歩き易い場所を行くと、小屋の北側のヘリポート前まで戻る事が出来た。このヘリポートに戻る直前、嫌なものを見てしまった。そこには大量の空き缶や電池等のごみがあった。おそらく小屋から出されたものであろう。何処の小屋も昔はこのように投棄していたのだろうが、それが現存しているのが見えるのはまずいかも。
小屋に戻ると、槍沢を見下ろすベンチで薮山さんとKさんがにこやかに出迎えてくれた。少し遅れる事、一眼を片手に抱えたI氏も到着し、早々に宿泊の手続きをする。私は素泊まりで6000円だった。食事付きで9000円。手続きを済まし、明日の為に下見とばかりに皆で小槍に近づく。私は何度見てもドキドキなのだが、猛者3人は至って普通の様子。経験からくる慣れなのだろうが、獲物を目の前にしたライオンか鷹のような勇ましさを感じるのであった。天気は良く、風もあまりない。明日が計画上の実行日であるのだが、一日目の今日も、過不足ない天気状態であった。ふとナビを見ると、日本山名事典の座標は、県境上の現在地のすぐ北側を指して、小槍としていた。そこはルンゼ内であり、少しの誤差を加味すると、小屋から大槍に向かう途中の、最初のピークに当たる。実際の小槍の位置は、北緯36度20分34秒・東経137度38分47秒辺りと読み取った。この場所は県境と言うよりは、完全に長野県側に入る。高山市には属さず、大町市のみの山となる。小屋に戻り一日目を終える。
素泊まりの場合、炊事場が新設の本館から離れた場所に設けられている。寒く暗く寂しい場所で、独りポツンと食事を取る。なぜがそこの下足はみな濡れており、シンクは水が出ないので汚いままであった。なにか新館の新しさとのギャップがあり、違和感があった。まあ南アの某小屋のように、外に出ないと火を使えない場所に比べればまだマシなのだが・・・。食事を終え、談話室で歓談が始まる。尽きない山談義、目の前に居た同志社大学の学生は、耳をダンボのようにしてこちらの話を聞いていたようだ。談話室の石油ストーブは暖かく、ヌクヌクできる快適な場所であった。消灯時間が迫り部屋に戻ると、同部屋の方は高岡カラコルムの重鎮と判った。トレードマークの長靴、そして持ち上げた日本酒「立山」で、まず間違いない。その立山を少し頂戴して、再び歓談が始まる。これが山小屋の横のつながりである。このような場面で、どれほど仲間が広がったか。20:30消灯。
翌朝は雨だった。皆、落胆のため息を吐く。少しぱらつく程度ならいいが、風を伴った冷たい雨であった。リーダーのI氏の判断で、8時まで待ってみる事にした。確かに東の空には明るさがあり、それを見ると回復傾向にあるように思えた。コーヒーを飲みながら時間が過ぎるのを待つ。途中行けそうに思える時もあったが、それは小屋が風を遮ってくれているからであって、いざ北側の西鎌尾根への下降点まで進むと、横殴りの雨が当たるのであった。8時を過ぎ8:15分まで引っ張ったが、状況変わらずここで正式に中止となった。この中止に異存はなく、この冷たさの中、まず登る自信は無かった。雨具を着込んで下山の準備となった。まあこんな時もある。場所が岩であり、ダメな時はあっさり諦めるのが岩屋だという。確かに命を賭ける場面が多いのだから、僅かなリスクでも諦める勇気が必要なわけである。ただこの時の雨は僅かなリスクでなく、多大なリスクであった。
一応今回のパーティーは、槍岳山荘で解散という事で、各々自由に降りて行く。雪渓の上をグリセードしながら飛ぶように下りて行く。先に出発した高岡カラコルムの長靴おじさんが居るはずで、氏を追いかけてゆく。しかし少し飛ばしぎみに降りてゆくが、なかなか掴まらない。かなりの健脚のようだ。高度を下げるに連れ天候は回復するが、それが「待っていれば」と思う事には繋がらなかった。振り返ると未だガスの中であった。
槍平小屋のテン場では、ヘリから降ろされた荷物を開梱作業中であった。ベンチの場所に行くが、そこにも長靴おじさんの姿は無い。常陸のパーティーが休んでおり、その前を早足で通り過ぎる。小さな沢の流れに沿うように水平に進んで行くと、おじさん発見。健脚のお姉さんもしっかり後ろに従っている。両名の後姿からは、只者でないオーラが出ていた。抜き去ろうか、このまま後に従おうか迷ったが、一か八か抜いてみた。するとおじさんは加速した。やはり凄い足の持ち主である。私も必死に逃げるが、足音が常について来る。しかし再び雨が降り出しスピードダウン。おじさんとのレースはそれこそ水入りとなった。
滝谷の渡渉点は、大きな角材を二本束ねた物で橋が造られ、渡りやすいように施されていた。この重い角材をどう動かしたのか。小屋番の努力に感謝しつつ渡って行く。チビ谷、白出沢越えるとその先はダラダラとした林道歩き。雨傘を片手に闊歩して下って行く。穂高平では、尾張ナンバーのワンボックスがあり、小屋の玄関が開け放たれていた。管理人なのか、開業するのか・・・。雨は依然止まず、木々の葉からボトボトと落ちる雨粒を傘で受けていた。ロープウェーの所まで戻ると、流石に賑やかになり、夏らしい周囲の様子となった。大型バスが行き交い、その窓からは周囲の緑に視線を延ばす乗客の様子が伺えた。それらの車の横をトボトボと行く。そして駐車場到着。出発時とほぼ同じ車が残っていた。
憧れの小槍は踏めなかった。簡単に踏めないから魅力が増す場所にも思う。直下から見て、全く無理な場所には思えず、何とか私の力量でも踏めそうに感じた。次回は是非、あの高みでアルペン踊りを披露したい。でも山頂部は浮石が多く、そんな余裕のある場所ではないような・・・。